よもぎ饅頭の昼下がり 前編
- すずめや

- 2025年12月8日
- 読了時間: 5分
つまんねえよなあ、とよもぎ饅頭は和菓子屋幸福堂の店頭で毒づいた。
もうずっとずっとつまんねえんだよなあ。
昔はちいちゃな子供が目を輝かせて饅頭を買いに来たってえのになあ。今じゃおいぼれのじじいかばばあか、しゃらくせえ気取った着物のやつがエラソーに買いにくるばかりだものなあ。
とはいえよもぎ饅頭は老人のお八つになることも、茶席の菓子となることも、べつに嫌だというわけではなかった。
顎の弱った老人が、それでも懸命に口を開けて、時にはやわらかく皺の刻まれた唇に触れながら、幸福堂自慢のつぶあんとよもぎの香りを楽しみながらじっくりと咀嚼してくれるのは喜ばしい気分だったし、凛と張り詰めた格式ばった茶席のなかの、ふと空気の緩むその一瞬を担えるのも誇らしい気持ちがした。
そういういつもの場所で、和菓子としての矜持が満たされると、よもぎ饅頭は一層ふっくらとするのだった。
それでもこんな晴れた平日の昼下がり、表のうぐいす色の暖簾の下からお天道様の光がすっと伸びてくるような頃合いには、そののどかさに釣られてあくびも出てきて、なんだか退屈な気持ちを持て余してしまうのだった。
少し前までは幸福堂の天井近くには小さなテレビが備え付けられていて、こういう怠惰な昼下がりには、パートの従業員と店内の和菓子たちとでぽかんと口を開けながらワイドショーのくだらない悲喜こもごもをぼんやり見ていたものであった。しかし老舗の幸福堂、店の体躯が古びて雨漏りを起こしてしまった。そして雨漏り修理のついでに店内をちょっとモダンに改装したので、小さなテレビはとっぱらわれてしまったのだ。今ではいくら和菓子が退屈していても、パートの従業員はひとりでうつむいて手元のスマートフォンをいじくるばかりになってしまった。
そうなってから退屈凌ぎに豆大福は、お互いの体にでっぱっている豆の数で賭けをした。
「勝負。おれの体の豆はいくつだ。」
「八個に賭けるぞ。」
「ならおれは六つに賭けるぞ。」
「じゃあおれは八個に乗った。」
そうしてまわりの豆大福は賭けの本人である豆大福のでっぱった豆をみんなでいーち、にーいと声を合わせて数えるのだ。
最中の皮などは、はさんだあんこを差し置いて、自分たちが挟むことのできる可能性のあるいろいろなものについての比較検討をしていた。
「もちろんいちご大福があるからには我々だっていちごを挟むことができるはずだね。」
「そうだ、そうだ。」
「ぶどうだってみかんだって挟むことができようね。」
「そうだ、そうだ。」
「否、そもそもだ、我々は大福そのものを挟むことだってできるのじゃないか。」
最後はいつもその話になって、そうすると最中の皮たちは自分がまるで世界の王さまになったような気持ちになって満足げにおっきな息をぷうー、と吐くのだ。
お赤飯はごまつぶとあずきつぶとでもち米のなかをもぐったり浮かんだりしておいかけっこをはじめ、肩寄せ合うわらびもちたちはこのねっちょりした体で僕らを食べようとする人間の鼻の穴に飛び込んでやったらどんなに愉快だろうねヒヒヒと笑い合い、真っ白い杵つきもちはただ目を閉じて瞑想をはじめ、悟りに到達すべく無我の境地へと旅に出る。
けれどよもぎ饅頭にはお外で風に揺られていた、お天道様の下でのびのびとのびるよもぎだったころの思い出があるので、そんなふうに他の和菓子たちのようにうちに篭った遊びにはなかなか楽しくは乗り切れないのであった。
「豆や米やらは元々きちんと畑で世話してもらって、さやにくるまれておっきくなったんだもの、野良育ちのおれとはちがわあな。」
するとおなかのなかの幸福堂自慢のつぶあんは答える。
「そんなさみしいこと、わたしと一緒になったんだからいいっこなしだよお。」
「でもなあおまえだっておれと一緒になったんだから、このつまんなさわかるだろう。」
「まあそりゃわかりますけれど、つまんないばっかりじゃつまんないしかないじゃないの。なにか楽しいことを考えましょうよ。」
そんなふうにしてまたいく日もいく日もがすぎてゆく。
その日は前日からざあざあぶりで、そのまま暗い朝が来て、お昼どきになるとからっと晴れた。よどんだ湿気がたちのぼって、また雨雲に戻ってやろうと我先にとお空を目掛けてゆく。
常連の爺さまが、雨傘をばさつかせたままその傘を杖がわりにカンカンついて幸福堂にやってきた。
「いやあ急に晴れたねえ。ざざぶりんなか出かけてうんざりしてたら。晴れて気持ちがいいからばばあになにか買っていってやろう。」
「ああよろしいことですね、できたての桜餅がございますよ。」
「ばばあそれ好きなんだよな、じゃそれふたつ。」
パートの従業員と爺さまとがそんな会話をしているなか、よもぎ饅頭の目の前で、じいさまの傘をまとめるボタンのついた紐がぶらぶらと揺れていた。そこでよもぎ饅頭は傘の紐に声をかけた。
「おいおい傘の紐ったら。」
「なんだい緑の。」
「ちょっと退屈してんだよ、もうちょっとこっちにぶらついてよ、この皿からおれを叩き落としてくれよ。おまえの爺さまじゃねえが、雨上がりの散歩と洒落込むんだよ。」
「ふうんべつにいいけれど、店のやつにめっかると爺さまが決まりわるいだろうからよ、うまくめっかんねえように転がんなよ。」
傘の紐は一仕事終えてせいせいした気持ちだったので、気前よくよもぎ饅頭のたのみを聞いて、うまくぶらついて皿の上からよもぎ饅頭をひとつ落としてくれた。
そもそも傘の持ち主の爺さまも、なんだかんだと理由をつけてしょっちゅう婆さまと一緒に食べるお八つを買いにくる常連だ。傘も持ち主の爺さまに似て世話焼きものなのであった。
よもぎ饅頭はうまいこところころ転がって、店内の人間の目に触れぬようにひっそりと幸福堂の外へ出た。
皿の上に残ったほかのよもぎ饅頭たちは口々に、オーイがんばれやーい、みやげ話をたのむぞお。と言ってよもぎ饅頭を送り出した。
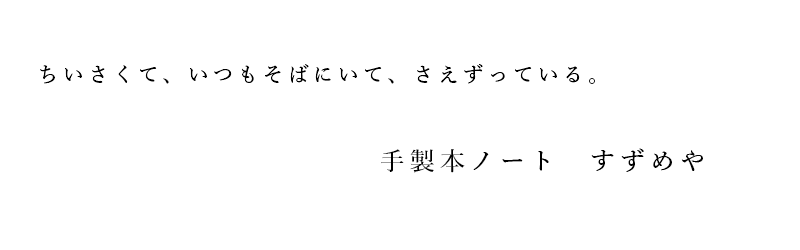





コメント