印刷
- すずめや

- 2025年7月26日
- 読了時間: 4分
あした印刷を頼んだ包装紙が届く。
ポストカードからノートや壁掛けパネルまで、ずっと原画だけでやってきたけれど少々の心境の変化があった。
ノートの表紙は近ごろ染める、というのがしっくりくる。
以前は描く、というのがしっくりきていた。
その変化はテクスチャアートのパネル作品を作り始めたあたりで始まったような気がする。
いまパネル作品は明確に描く、と思っている。
染めるというのは自然体な感じ、そのまま感じたまま絵の具をといてその先もまかせていくかんじ、描くと言うのは目標がある。
この色この質感で仕上がりはこんな感じ、くらいのなんとなくのものだけれど。
表紙を何万枚もやってきてるはずなので、ある意味でのカンストが来たのかなと思う。
カンストの一点を超えるとそれが自然の、呼吸とかと同じようなものになってくる。
製本作業がそれなんだけど、表紙を染めるのもそこまで来たみたいなかんじがする。
いつもなにかを身につけるには、わたしにはずっと"得られるまでひたすら続け続ける"しかない。
センスや技術をまるでギフトかのように才能、なんて言われたりすることもあるけれど、そういう天才は歴史に残るあらゆる偉人たちのなかでもたぶん本当にひと握りしかいないと思う。
才能なんてほとんどすべての人間にはない、筋トレと同じでやったかどうかと向いてる訓練かどうか、そういうことだと思う。
山に登ったことのないわたしは山登りをする人のことが本当にはわからないのだ。
歩き"続ける"ということに関して、ほんのちょっぴりだけ、わかるだけだ。
まあそれで話を戻すと包装紙を作るべく絵を描いてデータ化し印刷所に送ったものが仕上がり明日到着するのだ。
今回は描画方法はノートの装丁の手法だけれど包装紙になることを意識したので"描"いた。
印刷をいままで取り入れなかった理由は、まず単純に原画のほうが美しいに決まってるから。
それから作ってる感があまりにもないというのも大きい。
データを作ってあとは寝ていれば作品になって帰ってくる(多少の梱包や包装などの手間があるにしても)なんていうのは信じられないことだ。
文字通り手応えがない。
デザイナーさんらと話すと、印刷に出すということはそんなに単純な話ではなく、印刷所選びや印刷機選び、色の校正やデータと現物との擦り合わせ云々、本腰を入れてやればやるほど難しいものになっていくらしい。
しかしわたしにとっては、手を動かして作ることが作る、なので、実際印刷屋さんが刷ったものつまり作ったものに対してやんやと言うことはおそらくできない。
そういうハードルとも言えないようなちっちゃな柵があって印刷にかけてなかった。
しかしもう染めることが呼吸となり、まあ別にいつもやってるやつだしその一部がそうなってもいいかと思うようになった。
ブログまとめ本を作ってみたり、出張予定のDMを印刷所に出して作ってみたり、こないだの北海道のイベントでもイベント費捻出のためのオリジナルグッズとして描いたものをマルチクロスにして販売するため、印刷に出した。
そういうちっちゃな場数を踏んだことも大きい。
原画を使ってノートを作っているのがわたしにとって日常になりすぎた。
浅草のイベントで、隣のブースにいたカリグラフィーの作家さんに、このノートぜんぶ原画で手で作ってるってみんな知ってますか?!と鼻息荒く驚かれた。
いやあいちおう説明はしてるんですけど、との情けない返事しかできなかったが、手製本も原画での装丁も、わたしからしたらそんなもの見りゃいっぱつでわかりますでしょうが、と思うけれどだいたいの人はいっぱつでわからないし簡単に説明しても手製本とはいったいなんのことだろうかと首を傾げることになるのだ。
わかりづらいことをやり続けてるんだからもうまあどっちでもやってもいいかっていう気持ちになったというのもある。
原画と違って印刷になったらたくさんの人のところにとどけられるのだし、ジョバンニだって印刷所で働いていたのだからもういいかべつに、とほっそい草を口に咥えて口笛鳴らし、胸をそらせて両手を頭の後ろで組む、昭和のマンガに出てくる少年の如き心持ちである。

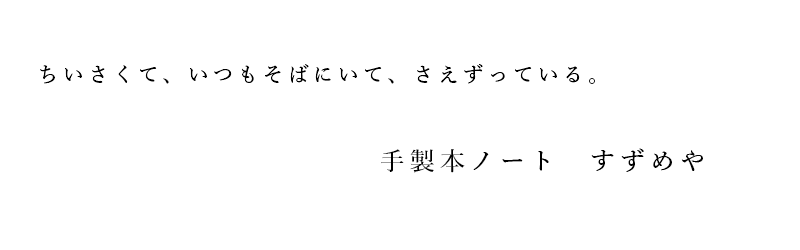







コメント