神谷バーへ
- すずめや

- 2025年7月21日
- 読了時間: 4分
仕事で2日間東京は浅草にいた。
前々からこの日はご飯にいきましょうと約束していた製本家の友人と、ふたりともかねてから憧れのあった神谷バーにいくことができた。
この出張に、集落のみんなでのBBQ会がかぶっており、行きたかったのにこんちくしょうと思っていたのでこの決定はとても嬉しかった。
東京住まいの彼女と現地集合に待ち合わせ。
わたしがひとあし早く到着し、恐る恐る入ってみると三連休中日ともあって人でごった返していた。
次から次へとやってくるお客が、店内をぐるりと回っては諦めたように出ていく。
店員さんは忙しく立ち働いているがそれにしても来店したものに対して特に注意を払っていないようだ。
いったいこれは…?と近くにきた店員さんを捕まえて聞いてみると、席は自分で自由にすわり、注文はカウンターにいって先払い、食券が発行されるので、それを持って席に戻るのだという。
聞いたことないシステムにキャリーケースを持っていたわたしはおろおろとし、席は満員、彼女はまだだ、彼女が到着するまでそのままおろおろと待っていると気の毒に思ってくれたらしい店員さんが空いた席を案内してくれた。
ちょうど角の隅っこで、根暗なわたしにとってとても安心できる場所が空いた。
座れたすぐあとに彼女が到着した。
いつもの仕事終わりのラフな格好とは一点、ベージュのうつくしいレースのワンピースに、薄青い刺繍の入った白い布の靴、口紅はかあっと赤く、思わず今日はドレッシーですね!と声に出すと、わたしと出かけるのでわざわざドレスアップをしてくれたのだそうだ。
なんと可愛いことだろう。
あれやこれやと食事と酒を注文する。
憧れの電気ブランを神谷バーで呑む時が来た。
なんかで読んだ、電気ブランのチェイサーはビールだというのを覚えていてビールと電気ブランを頼んだ。
たぶん森見登美彦で読んだんじゃないかといま思う。
神谷バーに憧れて大学時代は電気ブランを常備していた、と思っていたが森見登美彦のことを思い出すとこれはもしかして神谷バーだけでなくあの本に出てくる京都の大学生活へ対する憧れも大きかったのかもしれない。
わたしも京都の大学生だったので、妙にかぶれていた時期があったんだった。
実は彼女と話すときまだ少し緊張していた。
製本をやりはじめたころ、先人というのはほとんどいなくて、もちろん仲間もいなくて、しばらく経って見つけたのが彼女だった。
改めて歴を確認しあうとそうでもなかったんだけど、わたしからすれば手製本をたくさん作って生業としている作家の先輩というのは17年やってきたなかでも彼女ひとりで、だから、いつも少し緊張する。
しかし彼女はうつくしい服を着てドレスアップしてにこにこ笑いながらやってきてくれた。
だからもう、ちゃんと仲良く話したっていいんだぞと思えた。
妙に肉じゃがっぽい味のジャーマンポテトと、生ハムとサーモン、なすのしぎ焼きという謎の焼きなすをつつきながらいろいろ話した。
話がなんでか映画に及んで、するとバイオレンス系の映画の趣味が合うらしいことがわかった。
あれ見たこれ見たどうだったと盛り上がるうちにどうも彼女は思ったよりも酔っているらしいところが垣間見え、それも余計に可愛かった。
顔に出ないタイプなのか、それともいつもよりお化粧をしてきてくれたから酔いが隠れていたのかわからないけれど、レオンを見たかという話が会っているあいだ合計三回出たので酔っているのは間違いなかった。
二次会にはじめて磯丸水産にも行った。
出先のランチで使ったことはあるけれど、これがかの噂の磯丸水産。
彼女が好きだという蟹味噌の焼くのと、たこやきと、赤いタコさんウインナーと、焼きそばを食べた。
タコさんウインナーはきちんと顔が作ってあって、そのすべてが死んだような表情だった。その顔を見てげらげら笑ってくだらなくて楽しかった。
蟹味噌は蟹味噌っぽいけど蟹味噌ではない絶妙な味で、このよくわからない蟹味噌味がどうしても好きなんだよね、と彼女は言って笑っていた。
よき時間に店が閉まっておひらきとなり、わたしはお世話になっている妹の家までタクシーで帰った。
タクシーが出るまでずうっとにこにこ手を振ってくれている彼女は何度重ねても足らないほどの可愛らしさがあった。
妹のうちの最寄りのスーパーでおろしてもらい、手土産にまた酒を買って、おつまみも買って、お風呂をいただいて夜更けまでまた呑んだ。
なんだか妙に、ずっと楽しいお酒の日だった。

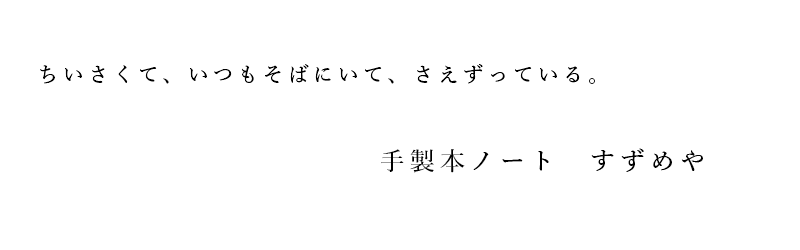






コメント