神さまんちの掃除
- すずめや

- 2025年9月28日
- 読了時間: 3分
もうすぐ集落の神さまのおまつりなので今日はみんなでおやしろのお掃除をした。
朝8時に集合してはっぱをかいたり燃やしたり、本殿を掃き清めたり拭き掃除したりしてぴかぴかにする。
ごりごりに神道、古の神道、というかんじで本殿に女性があがりこむのもぜんぜんありだし本番のお祭りではそこで酒盛りまでする。
はじめはそんなことしてええのかと京都時代の感覚を引きずってどきどきしていたけどなんかこれって普通でいいなあと今は思う。
神さまが身近な存在としてそばにあるかんじ。
その辺のお兄ちゃん、とまでいうのはあまりに不敬かもしれないけど、頼れるでかい兄ちゃんがそこにいる、くらいの温度感かも。
今日は掃き掃除のときに、御神体を触ってしまった。
御神体の下のとこを掃くからこれ持ち上げて、ということで御神体を持ち上げたのだ、さすがにこれはどきどきした。
深い紫色の神前幕を捲ると、褐色の肌ではちゃめちゃに怒り顔の筋骨隆々の男の神さまと、歯を剥き出しにして笑いながら赤ちゃんを片手に抱いた女の神さまがいた。
その笑顔はなんとも穏やかながら、それはさすがに笑いすぎやろ、と突っ込みたくなるような愛嬌があって、とてもとても、いい表情だった。
うちに帰って調べてみると、あの神さまたちは大山祇命(おおやまづみのかみ)と木花咲耶姫(このはなさくやひめ)であるらしいことがわかった。
山の神さまのお父さんと安産や多産の神さまの娘さんなんだそうだ。
わたしは子どもをもたないけれど、安産と言われてふと思ったのは作品のこと。
作家の中でもだいぶ物量を作るタイプだと思う、大量に毎日作り続ける。
それはある意味でのお産ではないか。
この集落にきてから、ぐっと作る量は増えた。
それはもちろんアトリエがばかでかくなったことによる作業効率の向上もあるだろうけれども、それにしても京都時代はなんだかんだと作れなくなって床に寝っ転がって虚無の時間を過ごすみたいなことがよくあったと思うけれどこちらにきてからそういう時間はほとんどなくなった。
新作にかかるときも、思案のための時間みたいなものがほとんどない。
他の作業をしながら考えて考えて手は別のものを作り続け、次の瞬間には新作にかかっている、というような流れ。
子どもをもたないのに安産の神さまのお膝元にいる、という後ろめたさももちろんあるけれど、木花咲耶姫について調べてゆくとなんだかどんどん、わたしのお産というのは作品づくりのことなんでないかと思えてくる。
木花咲耶姫の強めエピソードとして、火の中で子どもを産んだというのがある。
家計が火の車であったときも作り続けていたわたしの風景にリンクするではないか。
まあ半分冗談として、とにかくいい笑顔の神さまんとこにいるというのは気持ちのいいことだ。
あんなに笑っている娘さんのそばでめちゃくちゃ怒っているお父さんにもおかしみを覚える。
お祭りの本番には、わたしは福岡に行ってしまっているので立ち会えないけれど、神さまの顔が見れたし、本殿にもあがりこんだし、まあ今年はそれでよしとしよう。
来年こそは参加したい。
スケジュール管理が下手くそなのをどうにかしたい。

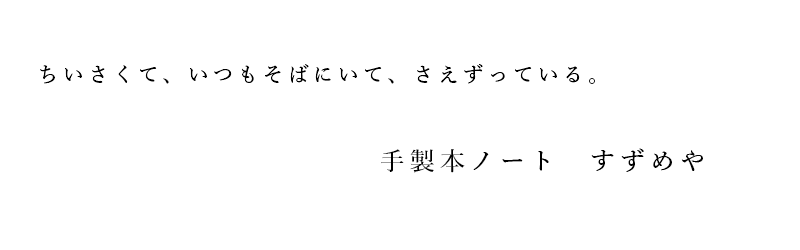







コメント