そうだったんでしょうか
- すずめや

- 2025年4月28日
- 読了時間: 3分
こないだの京都の展示に久しぶりに友人がきてくれた。
会ってはいたけどゆっくり作品を見てもらうのはすごく久しぶりだった。
その人は言語野がしっかりしているタイプなので感想を送ってくれた。
その感想が、近ごろなんだかもやもや考えていたことの輪郭をはっきりさせてくれた。
コロナ禍でメンタルダメージを受けて、その前まではちょこちょこ作っていた文章の作品を作らなくなった。作れなくもなった。
それまではわたしは詩人であるという自認があったように思う。
コロナで世界が変わって、移動もして、生活もまるっと変わって、その感覚はずっと遠くに行っていた。
最近作れるようになったもの、パネルに絵の具をこすりつけて絵を描いたもの。
部屋に飾るものならば、暮らしの中にいつもあるものになるのならば、押し付けるようなことはしたくなくてタイトルはつけずにいる。
なんにでもみえるように、世界はその時立っている場所によって見えかたがかわるんだから。
それから挑戦中の文字を描いた表紙。
宮沢賢治とマラルメは別格のひとたち。
なにいってんのかわかんないような難解な世界を持つ彼ら、なにいってんのかわかんないところが多いのにわたしの芯のあたりにいる。
そのふたりの詩と、言葉を、いま、毎日書き写している。
ことば、ことば、ことば。
つくっているものは、ノートという文房具である前に、作品です。
では、わたしのいう、作品とはなんでしょう。
香りたつようなもの、けむりのようなもの、そばにあって過ぎ去ってゆくもの、ぼやんとしたなにかに、ことばで輪郭を与える。
わたしは、詩を書くということは、ずっとそういうことだと思っている。
ずっとそういうことだと思っていたのに、自分のことをよくわかっていなかった。
わたしはずっと詩をつくっていたのだ。
白紙の世界をこの手で綴じて、彩りをあたえ言葉をあたえ、輪郭を持たせたのだ。
魔法を使うように言葉を使うのだ。
そして絵の具も使えるようになったのだ。
いち、にの、さん。
かっこいいだけでぶん殴るような作品を作る人に憧れた。
寡黙で静謐な作品たち。
同業の作家たちが製作のあるある話で盛り上がっているのを寂しく眺めた。
手製本には仲間が少ない。
先人が少ないと常に暗中模索の状態で、何も見つからなかった道もあった。
あかりが欲しくて媚びたこともあったし、騙されたこともあった。
それはわたしが、わたしの作るもののことを、よくわかっていなかったせいだったのかもしれない。
迷い疲弊し耐えて進む、そういうときには見えるものはすごく少ない。
たまにいただける感想のメールに、どうしてもぎゅうっとなってお返事が返せない。
それって自分がなにをしてるのか、ちゃんとわかってなかったからなんじゃないのか。
ちゃんとなにしてるのか把握しなきゃならない。
ことばで世界を捕まえる。
わたしは魔法使いの詩人である、という可能性がでてきた。
さてもそう言い切ってしまえばなんにでもなれる、ことばにはそういう力がある、さて、さて。
明日には名古屋に出発する。
空を飛んでゆく。

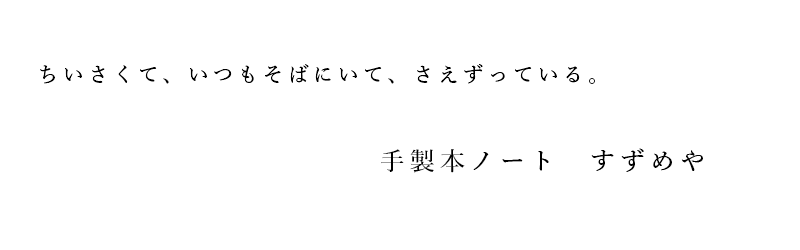






コメント